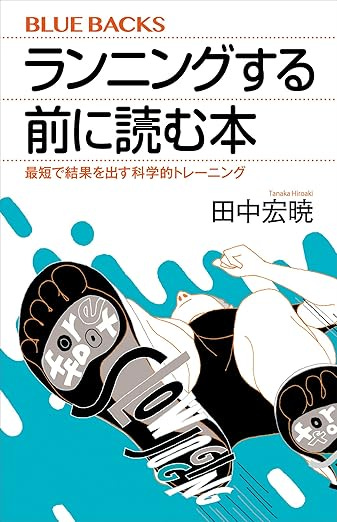「つらい練習が正解だ」という価値観を手放す
📅犬の散歩よりも遅いジョギングで速くなる
「なにもしない散歩」から得られる効率の良い一日を楽しんでいたごりゅごですが、今は犬の散歩よりも遅い「スロージョギング」を楽しむようになりました。
今回は、どうやってスロージョギングを知って、どう試して、どんなことがわかったのか。まとめてみます。
メインはジョギングの話ですが、きっともっと普遍的な「上達の話」につながる内容です。
「not for me」だと思ってたスロージョギング
実は、この「スロージョギング」というやつは、もうすでに2年くらい前から存在を認知していました。
きっかけはブックカタリストの読書会。そこで、読書会参加者のsanshoさんがこの本のことを教えてくれました。
→ 2023年10月読書会メモ(sansho) - BCBookReadingCircle
ただ、当時の自分はプールで泳ぐという運動をしており、いかに速く楽に泳ぐかが興味の主体。スロージョギング自体に関しては「へええ。そういうものがあるんだな」程度の興味は持ったけれども、今の自分には必要ないなという感想でとどまっていました。
そこから約2年。次はナレッジスタックのDiscordサーバーを通じて、再びスロージョギングとの出会いが訪れます。
ジンさんがデイリーノートの中で「スロージョギングを始めた」ということを書かれていたのです。
なによりも超タイムリーだったのが、ごりゅごがその話を目にしたのが「走って足を痛めた直後」だったということです。
もともと「へええ。そういうものがあるんだな」と思った程度にはスロージョギングというものにも興味を持っていたので、こういう運命は素直に運命だと受け入れ、自分も一度本を読んでみよう、と決意してみたわけです。
スロージョギングはBORN TO RUN式の走り方だった
元々は、あくまでも「ひとつの選択肢」としてスロージョギングという手法に興味を持っただけなんですよ。
調子に乗って速く走ったから、足を痛めた。
だから、調子に乗らずにゆっくり走れば、安全に健全に走って、ついでに心肺機能を高めることができるんじゃないだろうか?
その程度の軽い気持ちで手に取った本ですが、書かれている内容が、まあこれまでの自分の興味とストレートにつながっているものが多くて、プリズナートレーニングに続く「くっそ面白いものを見つけてしまった」状態になってしまったのです。
まずね、基本的な走り方が『運動の神話』なんですよ。
どういうことなのかというと『運動の神話』の著者ダニエル・リーバーマンが推奨している「フォアフット着地」というやつ。スロージョギングの本でも、この走り方が推奨されており、本の中の参考資料としてダニエル・リーバーマンの研究結果なんかも出てくるんですね。
(ちょっと古いですが、『BORN TO RUN』という本で紹介されて有名になった走り方がこれ。その中で、ダニエルリーバーマンの研究についても触れられている)
元々このフォアフット着地という概念や、ダニエルリーバーマンの主張には非常に共感していたので、まずその点でちょっと著者のことを好きになるわけです。
研究者も「自分の体」で実験してた
そしていろいろ読んでいると、この著者の方は「自分の身体を使って実験する派」の研究者の方なんだとわかってきます。
元々著者が最初にマラソンを走った理由が「運動のストレスとホルモンの関係を調べるため」
そのために自らを実験台にして、研究の材料にした、というタイプの人。
その後も、マラソン系の実験と、自身の練習を元にして「あと10kg痩せればマラソンのタイムは30分縮むはず」みたいな計算をして、実際に計算通りの結果を出して、自らの仮説を証明した、なんて話だったり、いろんなことを「自分で試す」人。
レベルは違えど、自分もこういう自分を使った実験みたいなやつは大好きで、その点でもまた著者のことを好きになってしまったりするのでした。
スロージョギングの本質はプリズナートレーニングと同じ
そしてなによりも一番面白くて興味深かったのが「遅く走った方が、短い期間で速く走れるようになる」という、ことばにしても文字で書いても意味がよく分からない不思議な現象。
本の内容を全部触れると終わらないんですが、あまりにも中身を省略しても意味が伝わらないので、ざっとまとめます。
まず、マラソンで重要なのは心肺機能である。これは、多くの人が直感的にも理解できるし、同意できるでしょう。
現在は「最大酸素摂取量」だとかアルファベットで「VO2MAX」みたいな名前で呼ばれるパラメータがあり、これが「心肺機能の代表的な指標」として用いられています。(Appleのヘルスケアアプリにもこのパラメータがある)
そして、著者らの研究により、この「最大酸素摂取量」(及び乳酸閾値)の値が、素人でもトップアスリートでも、あらゆるランナーのマラソンのタイムとほぼ相関している、ということがわかってきています。
これは、超単純に言うと「最大酸素摂取量」さえよくなれば、マラソンを速く走ることができるようになる、ということ。
そして、最大酸素摂取量を上昇させる一番の方法というのが「ミトコンドリアを鍛える」ことなのです。(これ、ブックカタリストで話した『肥満の科学』とストレートにつながる話です)
ミトコンドリアを上手に鍛える方法は、筋肉と同じで「ぶっ壊れない程度にたくさん使ってやる」こと。その中でも具体的な方法として「乳酸がたまらないギリギリの速さで走る」ことが、ミトコンドリアを一番効果的に鍛える方法らしいのです。
そしてここからが超面白いんですが「乳酸がたまらないギリギリの速さ」というのは、めちゃくちゃゆっくり走るだけで、めちゃくちゃ楽に達成できてしまうスピードなのです。(早歩きでこれを達成するのは困難)
ウォーキングでミトコンドリアを上手に鍛えるのは強度的にもとても難しいのに、走れば超ゆっくりで簡単に達成できてしまう。
結論だけを聞くと、なんか嘘なんじゃないかと思うくらい、楽ちんなのに効果が高い方法のようなのですよ。
一見すると超ラクなだけで効果的には見えない練習が、結果としてはもっとも効果が高い練習になる。こういう超簡単な練習をきちんと超丁寧にやることこそが、もっとも早く成長する方法になる。
これって、ごりゅごが感銘を受けた「プリズナートレーニング」の考え方と、ほとんどまったく同じ考え方です。
そう、スロージョギングは「ダニエルリーバーマン風プリズナートレーニングだった」という言い方ができるものだったのです。
遅すぎて犬の散歩してる人に追い抜かれる
じゃあ具体的に、スロージョギングとはどのくらいのスピードで走ればいいのか。
本で書かれている「ボルグの主観的強度」という数字はまったく当てに出来る気がしなかったので、初心者限定で通用すると書かれていた「心拍数を基準に走る」ことを試してみました。
目標心拍数は 138-(年齢÷2)
この計算でいうと、ごりゅごの目標心拍数は116bpm。
Apple Watchがあれば心拍数は簡単に計測できるので、Apple Watchをつけて、心拍数120を超えないことを意識してひとまず少し走ってみました。
まず最初の感想。
心拍数120というのは「ゆっくり走ったつもりでも一瞬で超えてしまう数字」でした。あまりにも遅いので「遅すぎて歩いてしまうくらい遅いスピード」です。
とにかくめちゃくちゃ「ゆっくり走る」ことを意識してスピードを抑制しないと、すぐにスピードを上げてしまって、心拍数が130とか140まで上がってしまうのです。
ちょっと油断しては心拍が上がりすぎ、やべえやべえとスピードを落とし、120以下の心拍を保って走ったペースは、1kmおよそ11分30秒。時速にしてだいたい5.2km/h。これは、普段ごりゅごが散歩して歩いているときよりもずっと遅いペースでした。
というか、一般的に散歩って時速4〜6kmくらいのものなので、本当にもう完全に散歩と同じペースです。
実際のところ、ジョギングしているごりゅごは、散歩しているおじちゃんおばちゃんたちにあっさりと追い抜かれていきます。
犬の散歩にも追い越されます。
これが、くっっっっそ面白い。
超ラクにたくさんのエネルギーが消費できる
自分の普段の散歩は(速く歩くことを意識して)1kmあたり10分を切るペース(時速6km以上)を目標にしていました。だいたいこれで4kmくらいの距離を歩いて、家に帰ってシャワーして休憩して1セット1時間、というイメージです。
ただ、この時は平均心拍数はだいたい100bpm。
それに対してスロージョギングは、1kmを11分半という歩くよりも遅いペースで走ってるのに、心拍数は120bpm。心拍数を元にして考えれば、スロージョギングの方が強度が高い運動であることはほぼ間違いないはず。
なのに、主観的な「大変さ」とか「疲れ具合」は散歩とまったく変わらないんですよ。
最初こそ「速く走らないようにするため」に、ずっと心拍数をモニタリングしていないといけなかったんですが、くっっっそ遅いペースに慣れてくると、散歩と同じくらいラクで、散歩と同じように「ゆっくり考え事をしながら走る」ことができるようになりました。
主観的な大変さは散歩と変わらない(超ラク)なのに、散歩より運動強度は高い。そして、多分、心肺機能も歩くよりも効率よく高めることができている。
おそらく人体の仕組みとしては「超ゆっくり走る」のって「効率が悪い」から、一定よりスピードが遅くなると、人は自然に歩いてしまいそうになります。そこを無理矢理人体の本能を抑えて、ゆっくり走る。これによって「つらくないのに強度が高い運動をする」ことができてしまうのです。(かつての人類は平均してごりゅごより心肺機能が高く、超ラクに走るペースが歩くことよりも十分に速度が速かったのだと思われる)
これを続けて心肺機能が高くなれば、超楽な状態のまま、より速く走ることができるようになります。
走った場合の消費カロリーというのは、ほぼ「距離」に比例するという研究結果もあるので、将来的に「速く走れる」ようになれば、同じような苦しさ(超ラク)なままで、今までと同じ時間で、より多くのエネルギーを消費することができるようになるわけです。
速くなくても超効率がいい(たくさんエネルギーを消費できる)のに、上達すればするほど、ますますラクなままで効率よくエネルギーが消費できる運動。ダイエットを目的にすれば、これ以上ないくらい最強の運動である、とさえも言えるのです。
「きつい」ことを乗り越える意味はあるのか?
この方法でなによりも面白かったのは「スピード」というよくある基準を一切目標にしないということでした。
一般的にランニングでは「速く走る」ことが「よいこと」であり、必然的に速く走ることが「目標」になりがちです。
そんなランニングを「心拍数を一定以下に保ったままで走れるかどうか」という方向に目的をずらしてやる。
これだけで「走る」ことは超ラクで、超面白いゲームに変化します。
「スピード」を目標にしてしまうと、他の人に追い抜かれることは屈辱ですが、心拍数を目標にしていれば、むしろ散歩している人々に追い抜かれていくことを面白がることができます。
(負けず嫌いの人ならば、俺の方が遅く動いてるのに、俺の方がたくさん運動しているんだぞすごいだろう、くらいに考えればいい)
正直、スロージョギングを試している期間が短すぎるために、本当にこの方法で「速く走れるようになるか」(心肺機能が効率良く上昇する)はまだわかりません。
若い頃はずっと運動部にいたので、未だに「きつい練習が成果が上がる」と考えてしまうマインドが残っています。こんなゆっくりで本当に速く走れるようになるのだろうか、といまでも少し考えてしまっているのも事実です。
さらに「苦しいトレーニングをしたことで成果を出した気分になる」という感覚も、よくわかります。「やったった感」は、きっと誰にだってある。
ただ『熟達論』にも出てくる話なんですが、苦しいトレーニングと技能の向上に相関はないということも、頭で考えれば確かにそうだと思うことはできます。(たとえば、ある場所から飛び上がる練習と、飛び降りる練習は、飛び上がる方がつらいが、飛び降りる方が負荷が高い)
ならば「心肺機能」が「技能」であるならば、苦しい練習なんて必要ないと言えるはず。
心拍数それ自体は、自分自身で意識的にコントロールすることはできません。だが、Apple Watchを見ながら走れば、心拍数を一定に保って走ることはある程度できる。つまり、技能によって心拍数をコントロールすることはできるようになるはず。
ならば「一定の心拍で走る」ということはまず「技能」と言ってもよいだろう。
あとは、練習によってこの技能が「上達」して「同じ心拍で速く走れる」ようになるかどうか。
いろいろ考えてみたんだけど、まあ結局わかりませんでした。
ただ、こういう実験はめっちゃ好きで、超面白いんですよ。練習の時間は必要だけど、その時間はとても面白いし全然苦しくない。だから、実際に自分で試してみればいい。
それである程度速く走れるようになったら、効果があったと言えるだろう。
そういう実験精神がある方が、むしろ自分は面白がって練習が出来るはずである。
これはあくまでも「大人の趣味」としての観点ですが、大人が自分自身の健康を主な目的として運動をしようと思うのであれば「苦しいこと」なんて限りなくゼロの方がいいと思うんですよね。
多くの人は「苦しいこと」よりも「楽しいこと」の方がモチベーションが保ちやすく、継続もしやすい。だから、苦しくない方がほぼ間違いなく健康にもよい。
さらに、心肺機能の向上に関しては「鍛えた量」がある程度重要になってくることはほぼ間違いない。それを「つらくて長い時間続ける」のか「ラクに長い時間楽しむ」かでいったら、自分はラクで楽しい方がいい。
自分もまだまだ「根性論」から抜け出せない部分があるんですが、今回の実験である程度の「結果」が出てくれば、もう一段階「ラクをして成果を出す」ことに自信を持てるようになる気がしました。
ここまでのことがわかれば、自分はもういくらでも楽しんで実験できます。
ラクに走って健康なら成功。
速く走れたら、それも成功。
つまり、なにを選んでも、たぶん失敗はしない。
陳腐で安易な基準から距離を置いた目標を描く
ちなみにこの「心拍数120をギリギリ超えない程度で走る」という目標は、本に書かれた内容を踏まえて、ごりゅごの解釈がかなり強く反映された目標です。
というのも、この本は2017年に出版されたもので、言ってみればちょっと「古い」んです。マラソンブームは始まっていたけれども、2015年発売のApple Watchはまだ一般には普及していたとは言いがたい状態。
心拍測定の方法がなかったとは言いませんが、走りながら心拍数を測る、というのはすくなくとも「手軽」とは言いがたいものでした。
本の中でも主な目標として説明されているのは「主観的強度」と「マラソンのタイムを元にしたペースで走る」こと。ごりゅごが言うような、心拍数を常に計測しながら走るという状況は想定されていないように感じました。
ただ、個人的にスロージョギングで一番重要なのは、「心拍を測って走ること」だと確信しています。
少なくとも自分は「ボルグの主観的強度」で走るペースを予測していたら、くっっそ速いペースで走ろうとして、絶対今みたいにゆっくり走ることを面白がれていなかった。主観的強度なんてものでうまく強度を分類できるような人は、もうその時点でかなり「ジョギングセンスがある人」です。自分自身の身体の状態を客観的にモニタリングする能力が高い人です。そういうセンスが足りない自分は、テクノロジーに頼って上達するしかない。
さらにいうと、自分はよい意味でも悪い意味でも「上達したい」という性質があって、これは上手く作用すれば素晴らしい効果をもたらしてくれるんですが、けっこういろんなことで「よくない効果」も発揮します。
水泳をやってた時も、やたらと「速く泳ぐ」ことを目指してつまらなくなっていたりとか、運動をやたらとスパルタ化しようとする傾向があります。
特にジョギングなんて、謎の「元陸上部」という自負によって、長距離選手でもないのに「速く走る」ことを目指そうとしてしまう。
だから、目標を「心拍数」に置くのです。主観的強度ではダメなんです。
心拍数を目標にすると、速く走れないんですよ。そして、心拍数を目標にすれば、遅くても、なんにも気にならないどころか、くっっっそ遅いことを面白がりながら走れるようになる。
歩いてる人に追い抜かれて「おおおおほんとに遅いな俺おもしれーーーー」みたいなことは「速く走ること」を目標にすると絶対に思えない。
速く走ってつらいことは「美しい」ことであるかのように感じ、すぐに結果を出そうとして、つらくて苦しい思いをして、つまらなくなってやめてしまう。
これまでも何回も同じような失敗を繰り返していますが、今回は久しぶりに「上手な目標」を自分で作ることができたと思っています。
「世間一般の当たり前」からはできる限り距離を置こうと思って意識はしているけど「自分の当たり前」を取り除くのはとても難しい。
こうやって「自分の当たり前」を取り外せる手法を見つけられるようにすることこそが「上達の秘訣」なのかもしれません。
(半年くらい続けられて、実際に上達したら、また続きを書いたりしてみたいと思います)